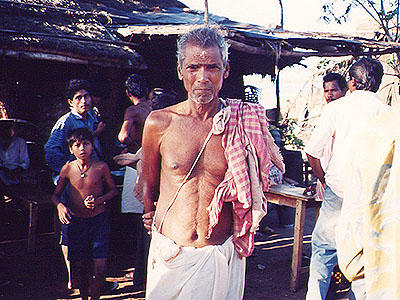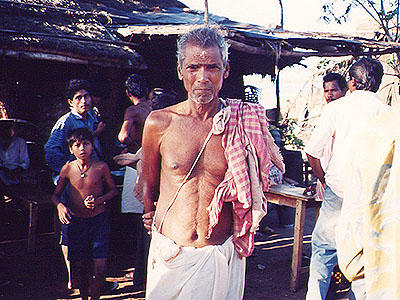インドなインド
最初で最後の1等寝台車。夜の内にプリーを出発し、朝方にカルカッタのハウラー駅に着くスリジャガンナートエクスプレス。これが最後の列車での移動になる。カルカッタに戻るのは、単に空港がそこにあるからというだけで、実質最後の土地になったプリーを後にする。
別段相談をしていた訳ではないのだが、偶然にもチャーと福庭さんと同じ列車になった。
福庭さん、というのは僕がサンタナで最も仲良くなった唯一の日本人だった。ある晩、ずいぶんと遅い時間に一人で夕食を食べているところに、たまたま出くわした。
「昼間は近くに見つけたゲーセンで1ルピー硬貨を費やして、日暮れ時からずっとガートを眺めていたんだ」
南をぐるっと回ってきたようだ。かなり髪も伸び、精悍な顔つきだったが、眼鏡の奥の目はどこかしらに笑みをたたえていた。
本の趣味がかなり一致していて話しが合ったというのがそもそもの発端だった。彼の薦めで本多勝一の「殺される側の論理」も読んだ。日本語の本がたっぷり読める、という意味では日本人宿も悪くはない。
一日を丸ごと使ってかれと60キロほど離れたチルカー湖へツーリングへ行った。宿で借りた原付に乗って。ガソリンスタンドなどないので、ペットボトルに予備の燃料を詰めて。淡水イルカが飛び跳ねる光景を期待していたのだが、沖合いへ出るためのボート代があまりに高すぎたのでそれはかなわなかった。しかし帰り道に、太陽がすっぽりと雲に包まれて、そこからが四方八方にあふれだし、それが平原に夕陽を投げかけていた。
もちろん、二人は2等寝台だった。
1等車は4人ずつの個室になっていて、鍵がかかるようになっている。寝台は2段になっているが、4つの扇風機がそれぞれのベッドに風を送るようになっている。両腕を広げても余りある広さ、とはいかなくとも、少なくとも寝返りを打つ程度の幅はあった。また足元にバックパックを置いても、足腰を折り曲げる必要はないくらいだった。しかしシート自体はビニール製で相変わらずベトベトとした不快感から逃れることはできなかった。それに窓が1.5倍ほどの広さであった。
しかし2等の3倍以上の料金を払うのは得心がいかない。再びインドを訪れることがあったら、やはり2等寝台専門でいこう。
30分遅れただけのまずまずの時間でハウラーに着いた。
まずは駅前で、目の前で揚げたばかりのプリーを頬張り、チャイを飲む。
市バスで久々のサダルへ。福庭さんは、混雑した車内では荷物に気を付けた方がいいと教えてくれた。実際、彼のザックは数カ所がナイフによって数十センチの幅に切り裂かれていた。店で修理してもらったその後は、まるでフランケンシュタインの手術の跡のように見えた。
まずはサルベーションアーミーをのぞいてみた。かなり清潔に見えたが、残念なことに男女別室だったのでそこはやめにした。
前回僕が泊まっていたホテルマリアのドミトリーはベッドが二つしか空いていなかった。結局、マリアからちょっと奥まった所にあるパラゴンへ。ここはインドの安宿の代名詞のような存在だ。
タバコの吸いがらや、ミネラルウォーターのボトルが散乱した床に、10個ほどの木製のベッドが並んでいる。これだけの部屋にファンは一つしか備えられていないが、それほど暑さは感じなかった。照明は裸電球が一つと、1メートルほどの長さの蛍光灯が一本。昼間でも薄暗い。
昨日、無茶な焼き方をしてしまったせいで、ひりひりする体を硬いベッドに横たえ、ごろごろとしていた。
チャーが「近くにチベット料理屋があるけど」と連れて行ってくれた。
パラゴンから数分歩くだけでこんな店があったとは。噛むとスープが飛び出すモモがうまい。麺にコシがあり、たっぷりの野菜がのり、スープも薄味ながらもしっかりとした味を持っているトゥクパも文句無しに最高。韓国系の人が経営しているのか、看板にはハングル文字が書かれていた。店の中には5、6人しか入る余裕はなく、外で待つ人もいるくらいだ。店の名前は、モモパレスという。
午後はサダルとチョーロンギーの角に建つ、インド博物館へ出かけた。最初のカルカッタ訪問の時、今川さんと長谷川君が「それはもう、まさしくインド」とそのおもしろさを目一杯語っていた。
確かに、それはもはや「インド博物館」と呼ぶよりは、「インド」博物館と呼ぶ方がふさわしい。入り口には昔の彫刻などが並んでいるが、その中に唐突に足の長いカニの剥製が陳列されている。布の展示の一角かと思えば、仏像に出くわし、「生活と植物」というコーナーには「ペンと鉛筆」というタイトルで放射状に並んだ色鉛筆が飾られている。また世界各国のコインが並ぶガラスのケースの中で、オーストラリアのものは2枚しかなかった。そんなわけはないだろう。
あるいはうす汚れたペンギンの剥製の背景には海が描かれているが、色を塗る作業が中断されている。
ずいぶんといい加減なものばかりかと思えば、逆に鉱石の展示は壮絶だった。各州で採取された色とりどりの鉱物の標本が、延々と広大な部屋に並んでいる。岩石に特殊な興味を持つ人以外は間違いなく途中で飽きるだろう。僕も早々に挫折した。
入り口からはそれほどの広さには思えないが、噴水を有する中庭を囲んだ建物は、歩いてみれば分かるがかなりのものだ。半日は軽くつぶせる。その気になれば2、3日かけて見物することも可能だろう。
しかし、おもしろいことは確かだが、つらい。そのカオス的思考システムは僕の理解の範疇を凌駕し、僕を疲れさせる。
パラゴンには日本人が少なからずいたが、僕が言葉を交わした範囲では学生はいなかった。大体、みんな4月に入ると帰国して行ったようだ。4月になって1週間が過ぎてもまだ居着く学生は僕一人だった。
カルカッタ最後の夜、福庭さんが数人の日本人に声をかけて「一緒に食事しようよ」と言ってきた。悪いけれど、僕は自身を含めて3人までならそれなりに会話に参加し、それなりに人当たりのよい人間としてやっていける。けれど、それを越えるとどうしようもなくなる。僕は勝手に混乱し、会話に口を挟むことすら臆病になり、沈黙する。特に初対面の人とはそうなりがちだ。無意味に気を使い過ぎるのか、自分をさらけ出すことも表層的にコミュニュケートすることもかなわない。人間関係において、中庸ということが苦手なのだ。
「最後なんだから一緒に食べようよ」と彼は言ったが、その無邪気な親切に対して申し訳ないと思うが、しかしそれでもうんざりとした感情を抱き僕は言った。
「最後だから、一人で食べたいんです」
これが僕の旅のスタイル。
贅沢に屋台のハシゴをして、しまいには缶ビールを買ってパラゴンへ戻った。ニューマーケットの横に2軒の酒屋を並んでいたが、値段が違った。人の集まっている方がもちろん安い。
飲酒が社会的にそれほど容認されていないからだろうか、新聞紙でくるんで商品を渡す。
出発の日、空港まではタクシーをシェアすることにした。フロントの掲示板に、ちょうど僕の出発の日付と同じ日の朝に同乗者を求める1枚のビラを見つけた。そこに部屋とベッドの番号、それに名前を書くように指示されていた。
「あなたなの?」とやってきたのは、若い女性だった。おそらく英語を母語とする人。インド人の英語には慣れたつもりだが、悔しいことにネイティヴの人間に通常の速度で話されると着いていくのが容易でない。とは言え、高度な政治問題や文化を論じるわけではない。所詮は事務的な話しなので、集まる時間をさっさと決めた。
当日は彼女と、もう一人の日本人男性もいた。彼は以前インドで暮らしたこともあって、言葉ができた。今回は会社の休暇を利用して出てきたのだそうだ。しかし休暇は1週間前に終わっているとのこと。
「先週の飛行機に乗るはずだったんだけど……。チェックインして、ロビーで搭乗を待っている間に眠りこけてしまって、気付いたら荷物だけ東京へ飛んでってしまったんです。何とか航空券の再発行はしてもらえたんだけど。とりあえず会社にはウェストベンガルでストが発生して飛行機が飛ばなかったと電話をいれたんですよ。いや、もう手荷物にはほとんど何も入れてなかったから、大抵のものを買い直しましたよ」
掲示を出した彼女は次はシンガポールに行くらしい。タクシーが動き出してしばらくすると、「Good-by India.」と静かに言った。
11時15分のフライトの予定が、空港に着いた時にはすでに電光掲示板には「15:30」という表示が出ていた。やれやれ、4時間遅れかと思ったのは甘かった。
当然機内食を期待していたので、インディアンエアラインズのカウンターで「昼食のヴァウチャーは出ないのか」と粘ってみたけど、やはり無理だった。
午後2時頃、無情にも予定時刻はさらに遅れて4時とになった。
大した設備もなく、僕は見送り用のラウンジで飛行機を眺めた。友人へのみやげにでもしようと思って買った、インド産のバグパイパーというウィスキーをちびりちびりとなめながら。
結局、5時間以上遅れて4時半にダムダム空港を飛び立った。
最後まで、インド的なインドであった。
ホームページ